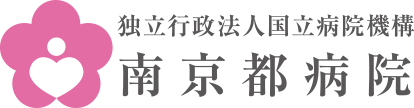薬剤部
薬剤部の主な業務
薬剤部では、患者さんに安心・安全にお薬を服用いただけるよう、調剤をはじめ、入院前の持参薬確認や入院患者さんの服薬説明、副作用・重複投与チェック、医薬品の適正使用における有効性・安全性の情報収集および情報提供、薬剤の無菌調製や院内製剤の作製等様々な業務を行っております。薬剤師の専門性を発揮して、より質の高い医療を提供することを目指しています。
概要(2024年度)
-
薬剤師数
7名
-
院外処方せん発行率
92.6%/月平均
-
薬剤管理指導件数
173件/月平均
-
病棟薬剤業務実施加算
204.8件/月平均
-
退院時薬剤指導
30.5件/月平均
-
退院時情報連携加算
4.2件/月平均
-
無菌調製件数
18.9件/月平均
-
処方箋枚数(内服+注射)
外来 387.8枚/月平均
入院 11528.6枚/月平均
-
認定取得
がん専門薬剤師(日本医療薬学会)
日本糖尿病療養指導士(日本糖尿病療養指導士認定機構)
漢方薬・生薬認定薬剤師(日本生薬学会/日本薬剤師研究センター)
KLEC認定薬剤師(近畿国立病院生涯教育センター)
NST専門療法士(日本臨床栄養代謝学会)
感染制御認定薬剤師(日本病院薬剤師会)
認定実務実習認定薬剤師(日本薬剤師研修センター)
GCPパスポート(日本臨床試験学会)
病院薬学認定薬剤師(日本病院薬剤師会)
調剤業務

当院では、電子カルテシステムが導入されており、処方に関しても調剤支援システムが導入され、連携して運用しています。
安全な薬物療法がおこなわれるように医師が処方入力時に自動的にチェック機能が働き、薬剤師は処方内容を確認し、調剤を行っています。
自動錠剤分包機による錠剤やカプセル剤の一包化や散薬監査システムおよび散薬調剤ロボットを導入し、調剤の効率化や調剤過誤防止対策を行っています。
患者さんが安心してお薬を服用していただけるよう努めています。
製剤と注射剤の無菌調製
診療に使用するお薬の中には、製薬会社が製造・販売していないお薬があります。院内特殊製剤は、病院内で審議し、承認されたお薬であり、薬剤部で作成しています。使用する際には患者さんに説明・同意を得たうえで投与を行っています。
★ 院内特殊製剤一覧栄養剤の一部(中心静脈栄養剤)や抗がん剤は、異物の混入や細菌による汚染、製剤の安定性に細心の注意を払いながら栄養剤はクリーンベンチ内、抗がん剤は安全キャビネット内で調製しています。徹底した安全管理の下行っています。
★ 抗がん剤レジメン一覧医薬品情報管理室
医薬品を安全かつ適正に使用するために情報収集を行い、院内の医療従事者に情報提供を行っています。医療従事者からの問い合わせの対応や緊急安全性情報(イエローレター)などの院内への通知や薬事委員会で採択された情報を提供しています。
薬剤師が日々の業務を遂行するのに必要な書籍や文献の集積・管理も行っています。
入退院支援センターでの持参薬確認業務
これから入院される患者さんの持参薬に関して外来での面談を実施しております。特に手術や検査目的入院の場合は、事前に服用を一時中止するお薬がないか確認を行っております。アレルギー歴やサプリメント等の服用の確認も併せて行っております。
外来での吸入指導
これから吸入器を用いて治療を開始される患者さんに吸入指導を行っています。また、以前より吸入器を使用しているが、再度薬剤師の確認が必要な場合も指導を行っております。1回30分程度で指導を行っています。
薬剤管理指導業務・病棟薬剤業務

呼吸器内科・外科や脳神経内科に入院されている患者さんに対し服用の説明・服薬状況の確認、持参薬の鑑別、副作用の確認等を行っています。また、薬物療法のリスクマネージャーとして職能を生かした事例についてプレアボイド報告を行っています。結核や副作用発現が心配されるような患者さんにおいては退院時にかかりつけ薬局へ情報提供を実施しています。
病棟担当薬剤師は、薬物治療の専門職として質の高い医療を提供すべく業務に従事しています。
チーム医療
栄養サポートチーム(NST)、感染防止チーム(ICT)、抗菌薬適正使用支援チーム(AST)、呼吸器ケアリハビリテーションカンファレンス、褥瘡対策チーム、医療安全管理委員会等のメンバーとしてチーム医療に参画しています。
臨床研究
日々の業務の中から生まれる疑問について、積極的に臨床研究をおこない、医療の発展に貢献できるよう励んでいます。同志社女子大学薬学部との包括協定に基づき、共同研究や相互支援を行っています。
★ これまでの実績教育業務
薬学生実習の受け入れ
当院は教育研修機関であり、その一環として薬学生の実習の受け入れを行っております。
実務実習(薬学5年生)においてはコアカリキュラムに沿って、早期体験実習(薬学1年生)においてはこれから先の学習の参考となるように実施しています。
-
・R6年度
早期体験実習18名 実務実習3名
-
・R5年度
早期体験実習14名 実務実習4名
-
・R4年度
早期体験実習 10名 実務実習 4名
-
・R3年度
実務実習 4名
-
・R2年度
実務実習 4名
スタッフの教育体制について
新規採用医薬品や治療ガイドラン等の勉強会を実施し、知識のアップグレードを行っています。また毎月症例検討会を実施し、薬物治療に貢献するための研鑽を積んでいます。
保険薬局へのご案内
平素は南京都病院の処方せん応需、運営並びに薬剤業務においてご協力いただきありがとうございます。
院外処方せんの疑義照会について
薬剤部では医局との合意のもと「院外処方せんの疑義照会簡素化運用について」を策定いたしました。策定内容に該当した場合は照会不要ですが、変更後に「疑義照会報告書」を病院までFAXしていただくようお願いします。
★ 2019.03.21 院外処方せんの疑義照会簡素化運用について(改訂分)また、通常の疑義照会は必ずお電話でお願いいたします。FAXではお受けしておりません。
-
月曜~金曜
8時30分~17時15分
-
月曜~金曜
17時15分以降
★ 院内採用医薬品一覧(2025年3月更新分)
院内フォーミュラリーについて
2022年よりNHOフォーミュラリー(院内)を導入しております
令和6年8月時点で10の薬効群において導入しています。詳細は一覧をご覧ください。
リファンピシン散の作製レジメンについて
当院で結核治療を受けておられる患者さんの中には、リファンピシン散での対応を必要とする方がおられます。当院ではリファンピシン10%散を作製しております。調剤の際にご参照ください。
<<リファンピシン10%散作製レジメン>>
| リファンピシンカプセル 150㎎×200カプセル(約36g) | |
|---|---|
| 乳糖賦形 | 264g |
| 合計 | 300g |
(リファンピシンカプセル200Cを脱カプセルして作製します)
退院される患者さんの情報提供について
当院で治療を終えて退院される患者さんの情報提供を実施しています(FAXにて送信)。
患者さんが退院後も安心して治療に専念するために非常に重要と考えています。
書式は日本病院薬剤師会が作成している薬剤管理サマリーを使用しています。
特に、入院中の経過や持参薬からの変更理由を始め既往歴、当院以外の病院名、治療に臨む気持ち、薬剤以外の使用物品や次回当院診察日も記載しています。
指導状況やご意見等を記載いただき返信をお願いいたします。
外来での吸入指導内容の情報提供について
吸入剤導入時のみならず、長年吸入剤を使用していても確実に吸入できていない患者さんにも外来での指導を行っております。
指導を実施した場合は、指導内容を書面にて情報提供しております。
吸入指導をされる場合にご活用いただければと存じます。
トレーシングレポート(薬剤情報提供書)及び吸入薬指導加算について
実施された場合は、薬剤部までFAXにてお知らせください。
送付先 FAX番号 0774-55-2765
★もし、疑問やご希望される事項がございましたらお気軽に薬剤部までご連絡ください。
企業医薬品情報担当者の方へのご案内
面談・面会について
薬剤部長へ面談・面会を希望される場合は必ず事前に下記アドレスもしくはお電話でご一報ください。
薬剤部医薬品情報専用アドレス:407-yak-1@mail.hosp.go.jp
TEL:0774-52-0065(代表)
・Webでの面談はTeams®もしくはZoom®でお願いします。
・面談時間は、平日13:30~15:30を原則とします。
・会議等の事情によりお受けできない日時もあります。ご了承ください。
医薬品医薬品情報活動について
-
①院内での情報活動に関しては事前にMR許可申請書を提出のうえで行ってください。
担当交代となった場合にも速やかに提出ください。
申請の際は、名刺を必ず添付してください。
領域別に担当者が配置されている場合は、領域担当者別での申請をしてください。 ★ 病院訪問許可申請 -
②新薬説明会
新規採用医薬品や治療ガイドラインの改訂等に関する勉強会をお願いしております。
開催方法は原則WEBでお願いいたしております。
開催時間は12時から30分、12時半からの30分の2部制です。この30分には質疑応答時間も含みます。資料等勉強会をするにあたり必要なものがありましたら事前配布をお願いします。 -
③包装変更や添付文書改訂等に関するお知らせは原則郵送での対応をお願いします。
-
④医師へ訪問される際は必ず事前にアポイントをお願いします。
ご不明な点あれば薬剤部へお尋ねください。